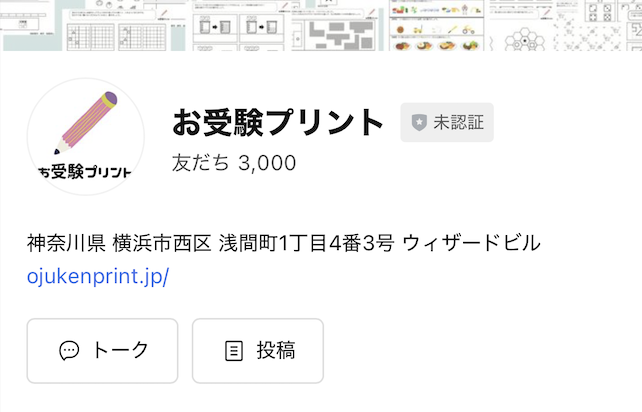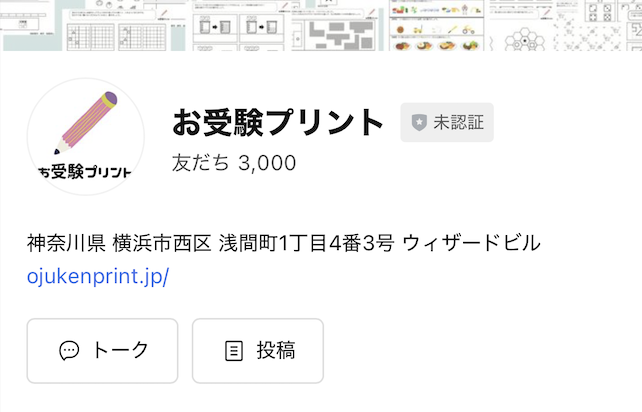※当サイトは一部内容を文部科学省、子供たちの未来を育む家庭教育、国立教育政策研究所を参考にしています。お受験プリントのプリントは理英会さんの「ばっちりくんドリル」、こぐま会さんの「ひとりでとっくん」シリーズの補助として活用いただけます。(運営元 : お受験プリント 運営事務局 〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目4番3号ウィザードビル)

リアルタイムアクセスのお知らせ!(*300秒毎に更新されます*)
一緒に頑張ろう!

近年、小学校受験において「行動観察」テストの重要性が高まっています。
このテストでは、子どもの社会性や協調性、課題遂行力など、学力だけでは測れない非認知能力が評価されます。
本ガイドでは、行動観察の目的や評価基準、家庭での練習方法などを詳しく解説します。
保護者の皆様が押さえておくべきポイントを網羅し、家庭での対策に役立つポイントをご紹介します。
お受験プリント STORE では、パック商品の期間限定で20% Off キャンペーン中!
割引セットご購入の場合は、最大で30% OFF となります。この機会にぜひご検討いただけますと幸いです。
*注意事項*期間2026/2/28(土曜日)まで。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察とは、集団遊びや指示行動を通じて、子どもの社会性・協調性・課題遂行力を測定するテストです。
具体的には、自由遊びや制作課題、ゲーム・運動、ディスカッションなどの活動を通じて、子どもの行動や態度を観察します。
行動観察テストには、以下のような出題形式が多く見られます。
学校によってはこれらを組み合わせた課題もあります。自由遊びの中にルールを加えたり、制作課題の中でプレゼンテーション要素を入れるケースもあるため、幅広い対応力が求められます。
近年、小学校受験の世界では「学力偏重」から「人間力・関係性重視」へのシフトが進んでいます。こうした中で注目されているのが、子どもたちの“非認知能力”です。
具体的には:
これらは、将来の学びや社会性の土台になるものとして、多くの有名私立・国立小学校が重視しています。実際、「正解を出せたか」よりも、「どう関わったか」「どんな姿勢で臨んだか」を評価基準にしている学校が年々増加しています。
行動観察では、子どもの「人間としての総合力」が問われます。特に私立・国立小学校では、集団の中で調和を保ちながらも、主体性をもって課題に向き合えるかという点が大きな評価ポイントとなります。
以下の5項目は、多くの小学校が評価基準として明示・明言している、または観察の中で重視している軸です。
例:「使いたい道具が他の子と重なったときに、自分から譲る」「誰かが失敗したときにフォローの言葉をかける」など、自然な関わりができているかを見ます。
例:「遊びのルールを提案する」「困っている子に声をかけて役割を与える」など、自分の役割を意識して能動的に動ける姿勢が評価されます。
例:「制作課題で材料の分配を考える」「完成に至るまで自分の作業スピードを調整する」など、行き当たりばったりでなく、流れを考えて取り組む姿勢が大切です。
例:「途中でルールが変わった際にパニックにならずに対応する」「失敗した友達のフォローに回る」など、臨機応変さと場の空気を読む力も重要視されます。
例:「椅子に正しく座り、話を最後まで聞く」「使用した道具を指示なく片付ける」「忘れ物をしたときに素直に申告する」など、日常の生活態度がそのまま現れます。
この5項目は、後述するチェックシートでも評価軸として使用しています。毎日すべてをパーフェクトにこなす必要はありませんが、週ごとに1つの軸に注目して練習・振り返りを行うだけでも、大きな成長に繋がります。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察で評価される力は、特別なトレーニングではなく、日常生活の中で自然に育まれるものです。しかし、意識的に「観察ポイント」を取り入れることで、成長のきっかけを与えることができます。
この章では、家庭で手軽に実践できる4つの基本練習をご紹介します。
兄弟や友達との自由遊びを10分間録画・観察することで、子どもの「社会性」や「自主性」を見える化できます。
観察・チェックポイント:
コツ: その場で注意するのではなく、後から「◯◯ちゃんがこんなこと言ってたね。どう思った?」と問いかけ、気づきを促すような声かけが効果的です。
特別な教材を使わなくても、家庭内の手伝いを小さな「観察課題」に変えることができます。たとえば:
ルール例:
遊び感覚で取り入れると、子どもも楽しみながら参加しやすくなります。
「フルーツバスケット」「だるまさんがころんだ」「イス取りゲーム」など、子どもに馴染みのあるゲームを使い、途中でルールを変更して適応力を観察します。
例:フルーツバスケット応用編
評価したいのは「完璧にできたか」ではなく、変化に対して冷静に行動できるかどうかです。
家庭で毎日「ありがとう」「どうぞ」などの他者を思いやる言葉が言えた瞬間を記録します。形式は簡単で構いません。
続けるうちに、自分の行動を意識する力(メタ認知)が育ち、「行動を選べる子」になります。
どれも特別な準備は不要で、日常の延長で取り組める内容です。ただし重要なのは、「大人が観察者として関わる姿勢」です。子どもを「評価する」ためではなく、良い変化に気づいて言葉で伝えることを意識しましょう。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察テストでは、「子どもが初めて出会う集団活動の中でどのようにふるまうか」が試されます。
ここでは、過去の出題例からご自宅でもご家族やお友達と取り組みやすい10問をご紹介させていただきます。
有料版のワークブックでは、各課題について、出題の意図・家庭での準備・練習時のポイント・減点されやすい行動を解説しています。
ここではサンプルとして、1つ目の例題を解説します。
課題内容: 制限時間内に、グループで話し合いながら「大きな一つの作品(例:花・家・動物など)」を折り紙で制作する。
目的: 協働作業における手順遵守・役割交代・集団の和。集団での制作活動を通じて、協調性・計画力・役割理解を養う。
準備物:
出題方法(例): 「今日は、おうちの人と一緒に折り紙で大きなの作品をつくってみましょう。どんな形にするか、相談しながら決めてください。折り紙は1人1枚使います。話し合って並べ方や役割を決めてね。」
進め方(ステップ):
観察のポイント:
声かけ例:
家族だけでやるときの工夫(2人〜):
お友達と一緒にやる場合の注意点(3〜4人):
ふりかえり記録欄:
減点対象の行動例(注意):
ワークブックでは、同様に「新聞紙タワー」、「ボール運びリレー」、「絵カードしりとり」、「お買い物ごっこ」、「積み木パターン再現」、「障害物チャレンジコース」、「共同絵本づくり」、「片付けレース」、「自己紹介サークル」の9つを同じように解説/紹介しています。
| # | 課題名 | テスト意図 |
|---|---|---|
| 1 | 大きな折り紙制作 | 手順遵守・協働 |
| 2 | 新聞紙タワー | 役割分担・創造性 |
| 3 | ボール運びリレー | ルール理解・協力 |
| 4 | 絵カードしりとり | 語彙力・順序 |
| 5 | お買い物ごっこ | 役割 |
| 6 | 積み木パターン再現 | 空間認知・模倣 |
| 7 | 障害物チャレンジコース | 運動協調・安全 |
| 8 | 共同絵本づくり | 表現力・協働 |
| 9 | 片付けレース | マナー・指示理解 |
| 10 | 自己紹介サークル | 自己表現・聴く力 |
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
小学校受験の行動観察において、保護者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。実際の相談事例や専門家の見解をもとに、具体的な対応策をご紹介します。
A:問題ありません。「関わろうとする姿勢」が見られればOKです。
行動観察で重視されるのは「社交的であること」ではなく、「関わろうとする意志」です。初めての環境で戸惑う子どもも多いですが、少しずつ距離を縮めようとする姿勢が見られれば、それは立派な成長の証。むしろ最初から積極的すぎる子より、慎重な子の方が評価されることもあります。
多くの子どもが、初めての環境では緊張しがちです。行動観察で問われるのは「完璧に話せること」ではなく、「関わろうとする姿勢」です。以下のような準備が効果的です:
緊張して話せなくても、“様子を見ながら少しずつ参加しようとする”だけで評価されるケースもあります。
A:協調型リーダーが求められています。
「自分が前に出る」タイプのリーダー像ではなく、「周囲に声をかけながらまとめる」協調型のリーダーシップが好まれます。指示を出すことより、人の話を聞き、必要なときにそっと助ける姿勢が高評価につながるのです。
リーダーシップ=声が大きい子、目立つ子ではありません。行動観察におけるリーダー像は「協調型リーダー」が理想とされています。
これらが“見えないリーダーシップ”として評価されます。「誰よりも目立たせたい」と考える必要はなく、他者と協調しながら進められる姿勢こそが求められています。
A:環境慣れとしては有効。必須ではありません。
プレ模試や行動観察講座に通うことで、「集団の中で行動する経験」を積むことができます。特にひとりっ子や幼稚園で自由遊びが少ない場合は、集団活動に慣れる場として有効です。親が評価するのではなく、第三者のフィードバックを受けられる点もメリットです。
「初見の大人・子どもとのやり取りに慣れる」という点で有効です。塾での練習には以下のメリットがあります:
一方で、通塾だけでは十分な対策にはなりません。家庭での過ごし方や、日々の積み重ねが重要です。塾を「自宅での学びを補完するもの」として位置づけましょう。
A:「教える」より「一緒に考える」姿勢を。
親が正解を与えるのではなく、子どもの行動を一緒に振り返ることが大切です。例:「さっきの片付け、どうすればもっと早くできたかな?」など、気づきを促す質問をすることで、主体性が育ちます。家族内での役割分担や感謝の言葉の習慣化も立派な練習です。
保護者が担う役割は、子どもを“訓練”することではなく、“気づかせ、見守る”ことです。以下のようなサポートが現実的かつ効果的です:
“教え込む”ではなく、“気づかせる”“引き出す”という視点でのサポートが、子どもの非認知能力を伸ばします。
受験対策は「特別な練習」よりも「日々の生活の中の気づき」が基本です。ご家庭でできることから無理なく始めていきましょう。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察の対策において、保護者や受験生がつい誤解しがちなポイントがあります。ここでは、代表的な誤解と、評価を下げてしまうNG行動を紹介します。
発言回数が多ければ評価されると思われがちですが、実際は発言の内容と周囲との関係性が重視されます。 周囲の話を聞かずに一方的に話す、他人の意見を否定するなどはマイナス評価に繋がります。 質の高い発言とは、「相手の発言を受けて展開する」「目的に合った発言をする」など、周囲との関係性を意識した言葉です。
多くの保護者が「発言回数が多い=良い評価」と考えがちですが、実際には内容の質と周囲との関係性が重視されます。
作品の出来栄えにばかり注目するあまり、他の子との関わりや工程の工夫が見過ごされがちです。 しかし、多くの学校では「結果」よりも「過程」が評価されます。例えば、他の子が困っている時に助けたり、自分のミスを報告して修正するなど、主体的で柔軟な対応が高く評価されます。
行動観察で制作課題が出ると、「作品の見た目」や「うまさ」に目が向きがちです。しかし、実際には制作過程での関わり方が見られています。
→ これは「聞く力」「従う姿勢」の不足とされ、減点の対象になります。行動観察では「静かに聞く→理解→実行」の一連の流れが大切です。
→ リーダーシップと支配欲の境界は紙一重。指導的な役割を果たす場合も、相手の気持ちに配慮した言動が重要です。
→ 行動観察は自然体での関わり方を見られています。練習のしすぎで“演技”になってしまうのも逆効果です。
いずれも自分中心の視点で動いてしまうと、集団活動における協調性に欠けると判断されます。
行動観察では、「完璧」な振る舞いではなく、周囲と調和しようとする姿勢が求められているのです。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察で問われる力は、短期間で一気に習得できるものではありません。
しかし、「今どの力がどれだけ育っているか」を可視化することで、練習の方向性が明確になります。
以下に紹介するのは、家庭で活用できる簡易チェックシートの例です。
1週間に1回程度、遊びや生活の様子を観察して評価します。
点数は“完璧さ”より“姿勢や成長”に注目してつけましょう。
| 評価項目 | 主な観察ポイント | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会性(協調性) | 順番を守る/譲る/相手の話を聞く | □ | □ | □ | □ | □ |
| 自主性(主体性) | 自分から活動を始める/提案する | □ | □ | □ | □ | □ |
| 課題遂行力 | 手順通りに取り組む/制限時間を意識する | □ | □ | □ | □ | □ |
| 状況判断力 | ルールの変更に対応する/困っている子を助ける | □ | □ | □ | □ | □ |
| 態度・マナー | 姿勢よく話を聞く/あいさつや片付けが自然にできる | □ | □ | □ | □ | □ |
お子さまと一緒に「できたね」「ここはどうすれば良くなるかな?」と話し合いながら記入することで、行動観察力=気づきと改善の力を養うことにもつながります。
お受験プリントストアにて、行動観察をご自宅で実践できるワークブックをご案内しています。全10問なので、ご家族やお友達と実践できるような内容になっています。
コチラの記事で、10問の問題タイトルと、掲載内容のサンプルをご紹介しています。ご興味頂けましたらワークブックも合わせてご覧ください。
行動観察は「点」で測れる力ではなく、日々の生活の中でじわじわと育っていく「線の力」です。
だからこそ、短期集中型の“詰め込み”ではなく、日常の中に観察力と実践力を育む視点を取り入れることが、最大の対策となります。
子どもが他者と関わり、試行錯誤しながら成長していく過程は、時にうまくいかず、親にとっても不安なものです。
しかし、「うまくできたか」ではなく「どう関わろうとしたか」「どんな気づきがあったか」を大切にして見守ることで、子どもは本来持つ力を自然と発揮し始めます。
本ガイドでご紹介したチェックシートや家庭練習法を、まずは1つでも良いので今日から始めてみてください。
無理なく、でも着実に。お子さまの“非認知能力”を育む道のりを、親子で歩んでいけますように。



お受験プリントは3000名以上の方々にご利用いただいておりますので、ぜひお試しください!(LINEでの宣伝はほとんどしておりませんので、ご安心ください笑)